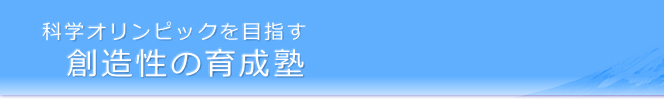こんにちは。私は、昨年第5回「創造性の育成塾」に参加させていただいた三吉真奈です。
私が現在暮らしている岡山県浅口郡里庄町は、原子物理学の父とよばれる仁科芳雄博士の生まれ故郷であることで知られています。
仁科博士は、1890年(明治23)年 岡山県新庄村浜中(現:浅口郡里庄町)に誕生し、第六高等学校を卒業するまでの23年間を岡山の地で暮らしました。
仁科博士の偉業を讃え、里庄町には科学振興仁科財団がおかれています。平成9年からは、仁科博士が留学されておられたヨーロッパへ、里庄中学校の3年生の中から数名が
研修生として派遣されるようになりました。私は今年、この海外研修生に選んでいただき、7月26日から8月4日まで、仁科博士の足跡をたどる旅をしてきました。
研修生は私も含めて計9名。
次のような日程で、大変貴重な経験をさせていただきましたので、報告させていただきます。
日程
7月26日 理化学研究所見学
7月27日 国立科学博物館・仁科記念財団訪問
7月28日 コペンハーゲンへ
7月29日 ボーア教授の研究所訪問コペンハーゲン大学訪問チボリ公園入場
7月30日 コペンハーゲン市内視察
7月31日 ロンドンへロンドン市内視察
8月1日 ケンブリッジ大学訪問とラザフォード教授のカベンディッシュ研究所博物館見学
8月2日 大英博物館視察とウィンザー城視察
8月3・4日 帰国
1日目~理化学研究所(埼玉県和光市)~
独立行政法人理化学研究所は1917(大正6)年に創設された物理学・化学・工学・生物学・医科学など基礎研究から応用研究まで行う日本で唯一の自然科学の総合研究所です。
仁科博士は、1918(大正7)年7月9日に東京帝国大学工科大学を首席で卒業し、翌日から理化学研究所の研究生になるとともに大学院工科に進学し、鯨井恒太郎教授の研究室に入りました。その後「仁科研究所」を立ち上げ、戦後の1946(昭和21)年11月から1948(昭和23)年2月まで所長を務めました。
仁科博士は、ここでウィルソン霧箱(気体中に霧滴をつくって荷電粒子の飛跡を観測する装置)やガイガーミュラー計数管(放射線検出器)、高電圧イオン加速装置の製作をしました。
1937年に小サイクロトロン、1943年に大サイクロトロンを製作し完成させました。
(注)サイクロトロン…荷電粒子を電場と磁場を用いて加速させる装置(加速器)
私たちは、まず、理化学研究所ができるまでの歴史を学びました。理化学研究所は、高峰譲吉(日本の科学者、実業家)と渋沢栄一(経済界の中心人物)の2人を中心にして設立されました。
2人は、「日本が立ちあがるには独自の技術が必要であり、その技術を持つためには総合研究所の設立が不可欠だ」と考えていました。そこで、理化学研究所設立の計画を練っていったのです。
そして、1917(大正6)年3月20日に設立することができました。
つづいて、森田浩介博士(113番目の元素を発見した)に「新元素の探索」というお話をしていただきました。 宇宙や地殻・人体は、どのような元素で出来ているのか、原子と原子核の大きさの比は、教室:ボールペンの先ぐらいの比であること、核反応とは元素の種類の変化であること、原子を壊すとどういった
反応がおこるのか、など専門的な内容を分かりやすく教えていただきました。
森田博士と一緒に超電導リングサイクロトロンの見学をしました。この超電導リングサイクロトロンは、全体が純鉄で覆われ、8300t(東京タワー2個分の重さ)
もの重さがあります。
この装置の中の構造は「史上最強のイオンビーム偏向能力」(8Tm)、「自己漏えい磁気遮蔽」「自己漏えい放射線遮蔽」の機能をもっています。
(写真左:超電導リングサイクロトロン)
これは、理研リングサイクロトロンです。この加速器を経て質量数60以下の元素は入射核破砕反応を起こせるまで加速されます。(写真右:理研リングサイクロトロン)
森田博士の研究室に、特別に入らせていただきました。ここで、113番目の新元素が発見されました。
2日目~仁科記念財団~
仁科記念財団は仁科博士が亡くなってから4年後、博士の業績をたたえ、優れた研究者を育成するという博士の遺志を継ぐため、吉田茂元首相が会長になって設立されました。
常務理事の矢野先生から仁科博士についてのお話と科学の歴史や相対論などの説明を受けました。そして現在、公益財団法人仁科記念財団の初代理事長を務められている小林誠博士と一緒に写真を撮らせていただきました。
また、実際に仁科博士が使われていたお部屋に入らせていただきました。当時のままで、その時の資料もあり、実際に仁科博士が使われていた黒板のレプリカなどもありました。(写真右)
7日目~キャベンディッシュ研究所博物館(イギリスのケンブリッジ)~
仁科博士が留学した当時(1921~1922)は旧キャベンディッシュ研究所で多くの学者が研究に励んでいました。その時の所長はアーネスト・ラザフォードで、そこで博士は原子の構造、放射能、原子核などの研究をしていました。
旧キャベンディッシュ研究所(1874~1974)は、ケンブリッジ大学内にありました。
ラザフォードは、物理学者、化学者で実験物理学の大家です。α線とβ線の発見、ラザフォード散乱による原子核の発見、原子核の人工変換などの業績により「原子物理学(核物理学)の父」と
呼ばれています。
現在のキャベンディッシュ研究所博物館を見学しました。旧キャベンディッシュ研究所の時とあわせると、ノーベル賞受賞者は28人います。
ここで、歴代の所長の研究内容やここの研究員だった学者たちの業績を詳しく教えていただきました。貴重すぎてとても展示できない、J.Jトムソンが使っていた真空放電管のレプリカや、実際に使われていた本物の実験器具なども見ることができました。
(写真左:J.Jトムソンが使っていた真空放電管のレプリカ)
J.Jトムソンは、物理学者です。電子と同位体の発見者であり、質量分析器を発明しました。 1906年に電子の発見と気体の電気伝導に関する研究でノーベル物理学賞を受賞しました。
キャベンディッシュ研究所博物館内で仁科博士がこの研究所に来た年に撮った写真を見つけました。
博士は2列目の一番左におられます。
4日目~ボーア研究所(デンマークのコペンハーゲン)~
ニールス・ボーアは1911年にイギリスへ留学、キャベンディッシュ研究所のJ.J.トムソンのもとでの研究後、1911年にマンチェスター大学のアーネスト・ラザフォードの元で原子模型の研究に着手しました。コペンハーゲン大学に戻り、マックス・ブランクの量子仮説をラザフォードの原子模型に適用して、1913年に
ボーアの原子模型を確立しました。
原子物理学への貢献により、1922年に37歳という若さでノーベル物理学賞を受賞。(写真左:ボーア研究所)
仁科博士は1923年に訪れ、5年間ここで勉強や実験をしました。博士は、ボーア研究所に集まってきていた若くて輝いている学者たちの言うことを一生懸命理解しようと努力し、追いかけて行きました。
そして1927年、「クライン・仁科の公式」をスウェーデンの学者、クラインと共同で研究を行いました。この公式は、電子と光量子との衝突の計算をして、量子力学の確かさをさらに証明するものです。
実際にボーア博士が使っていた書斎に入らせていただきました。机のまわりには、この研究所が始まった日に撮った写真がありました。
また、アジアのお土産やボーア博士が来日したときに仁科博士と鎌倉で撮った写真が壁にかけてありました。(写真右)
(1937年、ボーア博士が来日したときに仁科博士と鎌倉で撮った写真左)
随想
今回のヨーロッパ研修は、私にとって人生で一度しか経験できないような本当に貴重な体験だったと思います。
10日間でまわった、仁科博士に深く関係する場所や、そこで聞いた数々の貴重なお話―例えば、理化学研究所での新元素の発見に関する取り組みや、仁科記念財団での物理や化学理論のお話は、大変印象に残りました。
さらに、仁科博士に会ったことのない研究者の方々からも、博士は尊敬されているということや、後に続く学者の為に、より深い研究ができる環境をつくり、遺していかれた博士の偉大さをこの研修で学び、より深く理解することができました。
科学は、日々進歩しています。現在の文明は科学の力を活用することで成り立つことができているのは明白ですが、同時に科学はまだまだ疑問に埋め尽くされている学問だと思います。
だから、この学問を専攻し、研究を志すのであれば、強い精神力や忍耐力、物事をいろいろな視点からみてみる洞察力が必要だと思いました。
今回の研修で、仁科芳雄博士は常に世界を意識し、日本の物理学を世界レベルまで引き上げることに大きく貢献されたことが良く分かりました。
私の住んでいる小さな町が、日本はもちろん世界の学者の方々の中で有名な仁科博士の生まれ故郷 であるということをとても誇りに思います。また、初めての海外で、直接異文化に触れることができたこともいい経験になりました。英語で現地の外国人に話す機会がたくさんあり、自分の英語が相手に理解してもらえたことで、積極的に自分から
話す勇気をもつことができました。
これからは、興味を持ったことや「この分野に挑戦したい」と思うことには、積極的に学んだり、自ら行動して取り組む姿勢をとって、いろいろな経験を積んでいこうと思います。仁科博士のように、偉大な人物になることは難しいですが、仁科博士はじめ多くの学者の方々の研究に対する情熱に少しでも
近づければと考えています。
|