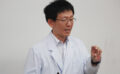理科室の入り口で、「石を一つ選んでから入ってください」と言われ、不思議がりながらも心躍らせる塾生たち。一人ひとり、拳ほどの大きさがある謎の岩石を目の前に、実験開始です。

今回のテーマは「化石から環境を探る」。学生時代は生物が専門だった内藤先生は、その面白さを子どもたちと共有したいと、中学の理科の先生になったそうです。授業では生物以外の分野も教える必要があり、そこで地学の魅力に気づいたとのこと。今では、どこかに出かける度に砂を拾って帰るほど、地学の面白さにはまっているそうです。

先ほど選んだ岩石を観察してみましょう。実はこの岩石は、約30万年前の地層の一部で、化石が含まれている可能性もあるそう!
まずは、表面を観察します。皆じっくりルーペを覗き込こんだり、触ってみたり。気づいたことをメモしていきます。そして、色や凹凸、粒の大きさといった特徴が挙がりました。

岩石は、火山灰や植物の破片、堆積物などで構成されています。
目の前の岩石には、どんなものが入ってるのでしょうか。
先生が割り方をレクチャーした後、塾生は、岩石の側面に見えている薄い層を割り始めました。

ハンマーで叩くこと数分。綺麗に出てきた葉の化石に歓声が上がります。昆虫の痕跡など珍しい収穫がある一方、なかなか見つからなくても、時に石を変えながら諦めずに、化石を探していました。なかには、あきらめかけた最後の一振りで急に化石が出てくるなんてことも。

筆で軽くクリーニングをしたら、葉の化石の種類の判定に挑戦。
配られたシートの絵や写真と照らし合わせ、化石の特徴を見極めると、ブナなどが確認されました。
「では、この地層はどんな環境で生成されたと思う?」と内藤先生は、問いかけます。塾生たちは、「ブナは寒いところにあるから、東北?」「そもそも火山灰があるなら、火山の近く!」など、様々な視点から意見が出ました。
実は、今回の岩石は、栃木県那須塩原市の「木の葉化石公園」のもの。火山に囲まれた湖の底のもので、きれいな地層は、流れのない湖で静かに降り積もった火山灰によって形成されました。先生は、「化石そのものの種類を類推することも大事ですが、そこから、地層が形成された当時の環境まで考察を巡らせることが大切」とおっしゃっていました。
たかが石、されど石。一つの石からは、とてもたくさんの情報が得られます。先生は、この実験を通して、化石発掘のわくわく感だけでなく、地層の背後にある世界の奥深さ、何よりも地学に目を向ける楽しさを伝えてくれました。
(14期生 梶川広樹)