創造性の育成塾> スペシャルコンテンツ ~OB・OG座談会~

今年も、新たな塾生を募集する季節を迎えました。今回、これから応募してくれる中学2年生に向け、育成塾のOB・OGが夏合宿を振り返る座談会を開催しました。
中学2年の夏から、それぞれ何年かの年月を重ねた彼らは、今、何を思うのでしょうか―
きっと、応募を考えているみなさんの背中を押してくれるはずです。
- 1期生(2006年)
- 佐々木 駿 東京大学大学院で植物生態学を専攻
- 2期生(2007年)
- 田崎 慎太郎 東京大学から昨年企業へ就職
- 貴田 浩之 東京慈恵会医科大学で医学を専攻
- 内山 桂一 藤田保健衛生大学医学部に在学
- 福田 宏樹 早稲田大学で地球・環境資源理工学を専攻
- 福永 健悟 東京大学で有機化学を専攻
- 3期生(2008年)
- 野田 康平 東京工業大学電気電子工学科に在学
- 4期生(2009年)
- 高倉 隼人 慶應義塾大学理工学部物理学科に在学
- 5期生(2010年)
- 矢吹 凌一 東京大学理科二類に在学
- 8期生(2013年)
- 太田 一毅 高校3年生
- 10期生(2014年)
- 山根 麻衣 高校1年生
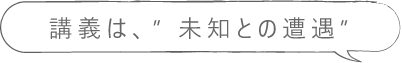
- 矢吹:
- 今日、当時のノートを持ってきたんですけど…
- 一同:
- お~! きれいに取っているね~
- 矢吹:
- ちょうど小林誠先生(※ノーベル物理学賞)の講義ですね。
粒子と反粒子の対消滅って書いてある。
電子という単語を中学校で学んだすぐ後に、陽電子って話になって…
当時は、「なんだこれは!?」っていう。 - 田崎:
- 数年後にOB参加して改めて講義を聞くと、すごく理解が深まるよ。
改めて、「こんなに高いレベルの話をしていたんだ」って思う。 - 福田:
- 実際のところ、講義の内容はわからないことだらけだったな…
- 貴田:
- 2期は、台湾の李遠哲先生(※ノーベル化学賞)が、
すべて英語で講義をされました。 - 2期生一同:
- あった、あった!
- 田崎:
- 講義の後、みんなで話して、
「みんな、あのレベルはわからないんだ」と却って安心した(笑) - 内山:
- はじめは、「隣の人はわかっているのかな」って
不安になったりしたけどね。 - 高倉:
- 参加する塾生は、中学2年までの段階で、
「わからない」っていう経験が少ないと思います。
育成塾の講義で味わった、ある意味の“挫折感”は
いい経験になったと思いますね。 - 内山:
- 学校の授業は、教科書に載っているからある程度予測は付くけど、
塾では何を話すのかわからない状況だった。
まさに、未知の世界でしたね。 - 貴田:
- あと、先生方が講義の最後に、中学2年生の僕らに向けての
メッセージを伝えてくれたよね。
それがすごく心に残っていますね。 - 一同:
- あ~そうだね。(うなずく)
- 貴田:
- 関本忠弘先生(※元NEC社長)の講義は、すごく印象に残っています。
創造性はどうやって育成するのかというテーマで、
それは偶然やひらめきではなくて…という お話をしてくださった。
自分の考え方が大きく変わるきっかけでした。

当時のノートを大切に保管していた矢吹君(5期生)
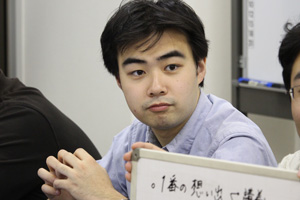
先生方のメッセージが心に残っている(貴田君・2期生)
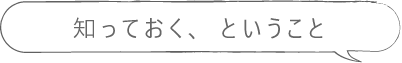
- 矢吹:
- 僕は5期生(2010年)ですが、その後の世代と決定的に違うのは、
東日本大震災の前か後かということなんです。
2011年3月11日から、シーベルトやベクレルという言葉が、
毎日ニュースに出てくるようになった。
その時、育成塾での木元教子先生(※元原子力委員会委員)の
講義を思い出しました。 - 矢吹:
- 放射線が身の回りにあることを知らない人が大多数の社会に、
ニュースでたくさんの情報が流れた。
「なんだ、なんだ」と混乱する中で、僕は、
少しだけど放射線について知っていたから、少し違ったんです。
単純に怖いだけのものじゃないし、常に身の回りにある。
講義でそれを知ることができたから、
「その量が増えて、大変なことになっているんだな」と想像することが
できた。「適切に怖がる」ということの大切さを木元先生も
話していたけど、“知らないことを知っておく”のはとても大事だと、
塾と、震災時に改めて感じました。

震災の時、塾で学んだことを思い出した。(矢吹君・5期生)
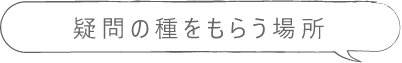
- 山根:
- 私は、育成塾に参加して、“全部完璧に理解して覚える”という
学校の授業とは違う、広い世界を知る経験ができて、
自分の世界も少し広がったかな、と思います。 - 福田:
- わからないとすぐに逃げてしまったり、
忌避したりすることがあるけど、育成塾では、仲間もいたからこそ、
“わからないことへの向き合い方”を経験できたと思う。
それがあったから、高校や大学へ進む時も、
わからないながらも色んなことを吸収できたりするよね。 - 内山:
- 講義の中でキーワードとして覚えていて、
大学で勉強している時に思い出したりするよね。 - 一同:
- あるある。
- 田崎:
- キラルとか?(※光学異性の性質)
- 福田:
- 黒田玲子先生(※東京大学名誉教授)の講義だよね。
- 内山:
- キラリティーね。すごく覚えてる。
- 福田:
- 大学に進んでも、どの分野でも出てくるよね。
わからないなりに記憶に残っていることが
後からつながってくるとか、そういうことは多いよね。 - 矢吹:
- 受験だと、制限時間が決められていて
その間で答えを出さなければいけないけど、
育成塾は、疑問を疑問として取っておく場所ですよね。 - 有馬塾長(※元文科大臣・元東大総長)が、
「生物の分野は、これから発展していく。面白いことが起きる」と
おっしゃっていました。
当時、僕は生物に全く興味がなくてピンとこなかったけど、
その後、高校で生物の授業を受けて、「細胞ってすごく賢い」
「まだまだ分からないことがいっぱいあるんだ」と、
面白さを見出していったんです。 - 振り返ると、有馬先生が話していたことが、少しだけわかったというか。
育成塾で得た疑問点をずっと持っておくというのは、
とても大事だなと思います。 - 田崎:
- 疑問の種をたくさんもらうってことですよね、育成塾は。

わからないことへの向き合い方を学んだ(福田君・2期生)
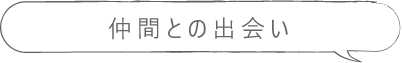
- 内山:
- 育成塾でよかったことといえば、
やっぱり、みんなと会えたことじゃないかな。 - 田崎:
- 再会した時に、ほんの1週間前に会った様な感じで話せる。
すごくいい仲間に会えたと思います。 - 事務局:
- 短い間の合宿で、そこまで親密になれるのはなぜだろう?
- 佐々木:
- まず、“科学や理科が好き”という共通点があって、
その上、全国各地から選ばれた人たちが集まった、というところから
結束感が生まれたんじゃないかな。 - 福永:
- なかなかいないと思うんですよね、中学で科学について話せる人って。
少なくとも自分の周りにはいなかった。 - 事務局:
- 部活の仲間ともまた違う?
- 田崎:
- 全然違うよね。
- 貴田:
- 僕のいた化学部は、あまり熱心にやっている人がいなかった。
唯一実験をやっていたのが、僕と森(2期生)だった(笑) - 田崎:
- 育成塾は、そういう人がたくさんいる集団ということだよね。

佐々木君(1期生)は、OB・OG会の会長でもあります。
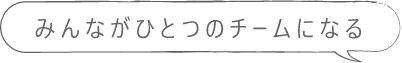
- 福田:
- あと、中学生の時に、学校行事以外で2週間も一緒に
寝泊まりすることってないよね。(※当初、夏合宿は約2週間実施) - 矢吹:
- 寝食共にするのは、学校に通うのとは全然違いますよね。
- 貴田:
- これまで自分がいた世界とは違う考え方の人や、
様々な出身の人たちと関わる経験をして、
自分の視界が開けたというか。そうした面白さはありましたね。 - 田崎:
- 育成塾の夏合宿は、結構詰め込んだカリキュラムですよね。
講義はもちろん、各講義のレポートやまとめも書かなければいけない。
それを、2期はみんなで乗り越えたんです。
わからなかったことを話し合って、
助け合いながらレポートを完成させたから、
チームのような感覚になれた。それが今につながっているのかな。 - 福田:
- 2期は、ロボットのプログラミングをする課題があって。
黒いラインをはみ出さないように動かすのがテーマだった。
それを二人一組で、三日間やると。 - 貴田:
- みんなで知恵を出し合って完成させよう、と盛り上がった。
あれを機に結束したかな。 - 高倉:
- 4期は、二人一組でパスタを使って橋を作る課題でした。
ペアだった塾生とは、翌年沖縄で会ったりして。
一緒に何かをしたっていう経験は大きかったと思います。 - 矢吹:
- みんなで作ると言えば、5期は、小林輝明先生の燃料電池でした。
コーヒーを電解液にして、燃料電池を作りました。
組み立ててテスターをつなげたら、全然反応しないんですよ。
電気が弱くて(笑)
結局、時間内に終わらなくて。まとめの時間に、みんなでつなげよう!と盛り上がったのが、すごく印象に残っています。 - 福田:
- やっぱり、コンセプトが「創造性の育成」ってところが
大きいと思います。
みんなで協力するプログラムがあることで、仲良くもなる。
自分だけで勉強していては、出ないアイデアもいっぱいあるし。 - 貴田:
- そうですね。
他の人のものを観察して、「あ、こいつすごいな」って思ったり。
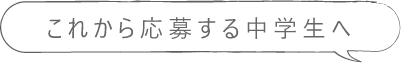
- 貴田:
- 応募する時は、僕自身、受かると思っていなかったんですよ。
- 一同:
- そうそう。
- 貴田:
- なぜかって、自分のアイデアが創造的なものだと全く思わなかったから。
僕と同じように、こんな考えじゃダメなんじゃないかと思って、
尻込みしている人も少なくないと思います。
自分で当たり前だと思っていることが、違う人から見ると
全く当たり前ではないことがある。
だから、尻込みせずに自分の考えを大切にしてほしいです。 - 内山:
- 文系の人や、理科が苦手だなと思っている人も、
チャレンジしてみると自分の新しい面に気付くことが
できるかもしれないよね。 - 福田:
- 意外と素人発想がすごかったりするからね。
- 矢吹:
- あと、A4の用紙に言いたいことをしっかりまとめるのも大変ですよね。
僕は、応募用紙を誰にも見せずに送りました。 - 福永:
- 自分も、どうせ通らないと思っていたから好き勝手書きました。
- 矢吹:
- これで、ちょっと自信を持ったんですよ。
高校の時は、自分の実験でレポートを書く時に、
コピーを取っておいた育成塾の応募用紙を参考にしたり。
「これで塾に選ばれたんだから」という自信が出てきて。 - 高倉:
- 僕はA4一枚に収まるように、すごく小さい文字で書きました。
- 一同:
- うなずく
- 矢吹:
- この白紙に、どうやって書くのか。
用紙の使い方にも創造性が問われてきますよね。
中学2年生で、こんな風に自分の考えを書く経験なんて無いですもん。

理系から離れた今でも、塾のことは思い出す(内山君・2期生)
夏合宿では、OB・OGがボランティアで運営に参加しています。
ここからは、その体験談を聞きました。
※今年もOB・OGの皆さんに、夏合宿にお手伝いいただく、
Teaching Assistant Programs を実施します。
詳しくは17.6.2配信の、事務局からのメール「『創造性の育成塾』事務局からのお知らせ(2017.6.2)」をご確認ください。
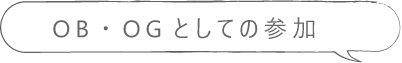
- 田崎:
- OB参加は、もう楽しいことしかないよ。
(※田崎君は、過去6回OBとして参加しています) - 貴田:
- 僕は、育成塾で受け取ったものがたくさんあるから、
今度は、それを返したいなと思って参加しています。
僕にかけてくれたお金や労力以上の価値を塾生たちに与えられたら、
協賛してくださった方々にも恩返しになるのかなと思って。
あと個人的な話ですけど、OB参加した時に、
塾生に向かって「その考えは、少し甘いんじゃないか」と厳しいことを言ったことがありまして。
その後、「言い過ぎたかな」と、気にかかっていたんです。
だけど、その子から「貴田さんの言葉で目が覚めました」と、
最終日のまとめの発表でお礼を言われたんですよ。
その時、「大変だったけど、また来よう」と思いましたね。 - 田崎:
- あれだけ素晴らしい先生方の講義をたくさん受けて、
最後に貴田の言葉が印象に残ったっていう(笑) - 貴田:
- あの時は、本当に気まずかった。
- (一同笑い)
- 貴田:
- 僕自身、今後、教育に取り組んでいきたいと思っているので、
教育方面に興味がある人もぜひ来てもらいたいです。 - 田崎:
- みんな後輩の育成をしたいというのは、少なからずあると思うんですよね。
研究者をしていても、民間に就職しても、中学生に関わる機会はあまりないので、今まで自分がやってきたことを伝えたいという思いを発揮できる機会は、育成塾しかないと思うんですよ。 - 福田:
-
中学生と話していると、絶対にこっちの考え方も問われるし、刺激になりますよね。
- 佐々木:
- 噛み砕かないと伝わらない。
噛み砕くことで自分の勉強をし直すことができて、
お互いに勉強になるよね。 - 高倉:
- 育成塾は、自分がサイエンスをやろうと思った大きなきっかけだったので、そこにOBとして参加することで、当時の自分がどんな気持ちでいたのか、初心に立ち返ることができるのは、ものすごく大きなことだと思います。
また、夏合宿で講義レポートを書かせていただいていますけど、大学生が聞いてもレベルが高い内容を、一般的にわかりやすく伝えるということもなかなかない経験で、重要なスキルが身につくと思います。
(※OB・OGは、夏合宿のページに掲載する講義レポートを担当しています) - 貴田:
- 講義を聴きながら書いていって、わかりにくいところを添削してもらって。あれで、文章を書く力がつきましたね。
- 田崎:
- あと、中学2年生の時は、わからないことだらけだったから、
「あの頃わからなかったことを、もう一回聞きに行こう」という気持ちは大きいですね。 - 矢吹:
- 僕、当時小林先生の講義を受けたから、今年聞きに行こうかな…
- 高倉:
- やっぱり大学に入ると自分の分野ばかり目が行くので、別の分野の話を聞くのは、貴重ですよね。

ミスター育成塾こと田崎君(2期生)
座談会はここまでです。
参加してくれたOB・OGのみなさん、ありがとうございました。
