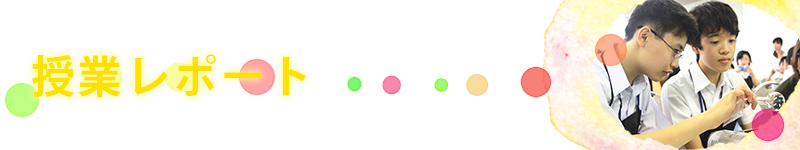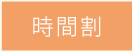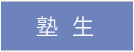8月3日 1時間目(9:00~)
筧 捷彦 (早稲田大学 教授)
情報・数学オリンピックについて

情報オリンピック日本委員会設立時から理事を務めている筧先生。
まずは、情報学について知ってもらうため、塾生たちに小中高生向け国際情報科学コンテスト「ビーバーコンテスト」の問題に挑戦してもらいました。

この時間のテーマは、中学校で習わない情報学がどのようなものか、そして、情報オリンピックがどのような大会なのか。
問題を解くためにどんな方法や順番があるのか考えることが、情報学の第1歩です。最小公約数の問題を例に、詳しく解説していきました。
同じ答えを得るのに、方法によって効率が大きく変わってくることがあります。
「やり方はいくらでもある。その中で1番効率の良いものを見つけましょう。それが情報学です」と筧先生は語ります。

こうした計算をコンピューターに実行させるための指示が、プログラムです。 コンピューターの小型化で、計算速度の高速化がさらに進んできましたが、チェスの完全な必勝手順など膨大な組み合わせを検査するには、宇宙の誕生以上の時間がかかるといいます。 さらに、人間の脳で行われている言語の理解・翻訳など、プログラムでできないものが存在するといいます。

講義の終わりでは、情報オリンピックについて紹介していただきました。 情報オリンピックは、与えられた問題に対してどれだけ効率の良いアルゴリズムを作れるかを競う大会で、中学生の入賞も珍しくないそうです。 今年の日本代表の中にも、中学生の時から参加し、金メダルを獲得した選手がいるそうで、塾生たちからも驚きの声が上がりました。

講義の終わりで、筧先生は2018年の情報オリンピックは日本開催であり、「将来有望な皆さんにぜひ参加してほしい」と塾生たちにエールを送りました。
(5期生 塩見 亮介)
講義映像
※講義動画の公開は終了しました。