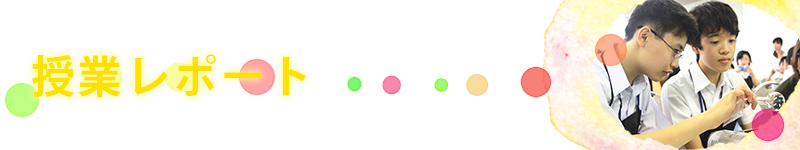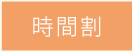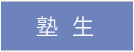8月6日 1時間目(9:00~)
下田 治信
(国分寺市立第一中学校 教諭)
飛ぶ種を研究しよう
植物は自分で生きる場所が選べない、という先生のお話から講義が始まりました。 種子が落ちた場所で一生を過ごさざるを得ないため、植物はできるだけ遠くへ種子を飛ばしていく仕組みを持っています。

まずは、いろいろな植物の種子を運ぶ工夫の紹介です。
例えば、タチツボスミレやカタクリ、ムラサキケマンなどの植物は、熟した実が弾けることで種子を撒き散らしますが、それだけでは終わらず、種子の表面に付着しているエライオソームという甘い物質によりアリに運んでもらいます。

続いて登場したのは、種子を高いところから落とす樹木・シンジュ。まずは、その種子の落ち方を観察し、飛び方の特徴を考えます。その後、細長い紙を使って同じ動きをするモデル作りに取り組みました。

なかなか思い通りの動きをせず悪戦苦闘していましたが、紙にひねりを加えるなど各自が工夫し、本物のシンジュの種子と同じように落ちるモデルを作り上げた塾生もみられました。さらに、先生から簡単な作り方の説明を受けると、「こんな単純な加工だけできれいに落ちるのか!」と感嘆の声があちこちから上がりました。

次に、フタバガキの種子が紹介されると、留学生からインドネシアではよく見かけるという話が聞かれました。フタバガキの名前のとおり、種に2つの羽根のようなものが付いています。その珍しい種を、再現しようというのが、今回の講義の目玉です。発泡スチロールの薄いシートを使って、羽根の形状やおもりの重さなどを工夫しながら、風洞装置の中で本物の種子と同じ動きをするモデルを考えました。

先生からは、できるだけゆっくり落ちるように工夫してみましょうという課題が出され、塾生は風洞実験を繰り返していました。最後には空中で回転しながら同じ位置にとどまるモデルを作り出す塾生も現れ、そのきれいな回転に周囲の視線が集まっていました。

最後に学ぶのは、カエデの種子。この種子はひとつでは飛ばず、ふたつ一組になった状態できれいに飛ぶことを学びました。こちらの種子も同じく発泡スチロールシートでモデルを作ります。先生によるとこの種子の動きを再現するのが最も難しいとのこと。塾生は短い時間の中で果敢に挑戦していました。

先生は、「今日はただ綿毛のように飛ぶだけでなく、いろいろな飛び方をする種子を見てきました。植物は、いろいろな工夫をしながらバランスよく飛ぶ種子の形を獲得してきたのです。みなさんも、たとえ失敗が続いても少しずつ改良していくように心がけてください。そして最後まであきらめずにやるということを学び取ってほしいです。」と結びました。
(2期生 田崎慎太郎)